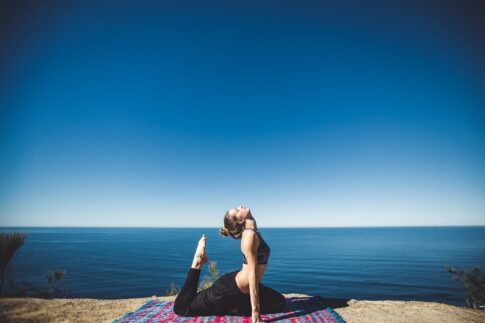マインドフルネスがメンタルヘルスに効果があることは、今や世界70億人で知られている話でしょう。(盛りすぎ)
おそらく、あなたはマインドフルネス情報を調べていて、メンタルに良いなら、悪い性格も変えてくれるんじゃない?って疑問を持ったことがあるのではないでしょうか。
今回は科学的な根拠をもとに、マインドフルネスが性格を変えるのか?その真相について見ていきたいと思います!

Contents
マインドフルネスで性格が変わる?
結論から言うと、
- マインドフルネスで性格は変わります。
なぜかというと、マインドフルネスは直接脳に影響を与えるから。
性格とはそもそも何を意味するか。コトバンクによれば、以下のように説明されています。
せい‐かく【性格】
1 行動のしかたに現れる、その人に固有の感情・意志の傾向。「ほがらかな性格」「夫婦の性格が合わない」
2 特定の事物にきわだってみられる傾向。「二つの問題は性格が異なる」「趣味的性格の濃い団体」
つまり、気持ちや行動の傾向ということ。
言わずもがな気持ちや行動は、脳の機能のよるものであり、脳が変われば必然的に性格も変わると言えます!
これが証拠-マインドフルネスで性格が変わった研究結果
さっそく本当にマインドフルネスで性格は変わるのか、研究から見ていきましょう
自主性・協調性・自己超越が高まる
Campanellaら(2014)[1]の研究では、41 名を対象にマインドフルネス瞑想が以下の性格特性に与える影響を調べました。
- 自己志向性(自主性)
- 協調性(周囲と協力できる)
- 自己超越(自分を超えた感覚)
自己超越はわかりにくいかもしれませんが、この特性が高い人は、他人や世界とのつながりを感じており、人生には自分よりも大切なものがあると認識しています。
この研究では、
・参加者を長期間 (1 年) にわたって追跡
・24 か月間3 つのマインドフルネス瞑想トレーニングをうけてもらう
・15 人がコントロール群(瞑想トレーニングを受けない群)
その結果、コントロール群に比べて、瞑想トレーニングを受けた群は3つの性格特性が大幅に高まったことがわかりました。

誠実さが高まり神経質が減る
Tamara L. Giluk(2009)[2]の研究では、マインドフルネスとBig5 の性格特性の関係について、29 件の研究の 32 サンプルから得られた結果を精査しました。
Big5とは、人間性格を5つに分類する性格分析でもっとも信憑性が高いとされています。具体的には、以下の5つの特性があげられます。
1. 開放性
- 新しい経験やアイデアに対して好奇心旺盛で、積極的に取り入れようとする傾向
- 想像力豊かで、創造性が高い
- 芸術や文化に関心を持つ
- 複雑な概念を理解するのが得意
- 型にはまらない考え方を好む
2. 誠実性
- 責任感があり、計画的に行動する
- 勤勉で、努力家
- 秩序正しく、几帳面
- 規則やルールを守る
- 目標達成のために努力を惜しまない
3. 外向性
- 社交的で、活発
- 人と話すことが好き
- エネルギッシュで、行動的
- 刺激的な環境を好む
- リーダーシップを発揮する
4. 協調性
- 親切で、思いやりがある
- 他者と協調することを大切にする
- 信頼できる
- 許し上手
- 争いを避ける
5. 神経症傾向
- 不安や心配を抱きやすい
- 感情的になりやすい
- ストレスに弱い
- ネガティブな思考に陥りやすい
- 孤独を感じやすい
その結果、すべての特性がマインドフルネスとかなりの関係を示しており、そのなかでも
- 神経症傾向
- 誠実性
はもっとも強い関係を示したことがわかりました。
つまり、マインドフルネスを行なうと、不安やストレスに強くなり、責任感をもって計画的にコツコツ物事をこなす傾向が強くなると言えるでしょう。
その他の研究
Crescentiniら(2018)[3]の研究では、被験者のうち17人には、8週間の瞑想トレーニングコースを受けてもらい、残りの16人は対照群で瞑想トレーニングを受けないでもらいました。
その結果、瞑想トレーニングを受けた群は
- 自主性
- 協調性
- 誠実性
が高まることがわかりました。これらは先ほどご紹介した2つの研究結果と同じ傾向を示しています。自主性・協調性・誠実性の部分は性格が変わると考えられます。
なぜマインドフルネスで性格が変わるのか
マインドフルネスが性格を変えるメカニズムは、まだ完全には解明されていません。しかし、いくつかの研究結果から、以下のような可能性が考えられています。
①脳の活性化
マインドフルネスを実践することで、前頭前野や海馬などの脳の領域が活性化することがわかっています。これらの領域は、思考、感情、意思決定などの機能に関与しています。
特に前頭前野は理性的な活動を司っているとされ、感情コントロール力が高まり、不安感の軽減や誠実性の向上に繋がると考えられます。
②セルフアウェアネスの向上
マインドフルネスを実践することで、自分の思考や感情を客観的に観察できるようになります。これは、自己認識の向上につながり、自分の性格や行動パターンをより深く理解できるようになります。
その結果、脳の活性化と同じように感情コントロール力が上がり、不安感の軽減や誠実性の向上に繋がると考えられます。

③自己受容が深まる
マインドフルネスを実践することで、ありのままの自分を受け入れることができるようになります。これは、自己受容の促進につながり、自分自身をより肯定的に捉えられるようになります。
自分の不完全さを受け入れられるようになるため、人に助けを求められるようになり、協調性が高まると考えられます。
マインドフルネスで性格を変える方法
ここではマインドフルネスで性格を変えるため実践方法について解説していきます。
とにかく継続!
身も蓋もない話ですが、一朝一夕で性格が変わることはありません。毎日少しでも良いので、マインドフルネスを実践する習慣を身につけることが大切。
毎朝5分間、瞑想を行う
1時間に1回、深呼吸をする
食事や散歩など、日常の活動中に意識を集中させる
マインドフルネスに関する書籍やアプリを活用する
最初は難しいと感じるかもですが、毎日続けることで、徐々にマインドフルネスが日常に溶け込んでいくようになります。
関連記事
マインドフルネス瞑想が続かない…継続・習慣化の5つのコツ
運動と組み合わせる
Stephanら(2018)の大規模な研究[4]では、約6000人のデータを分析し、運動量と性格の関係について調査しました。
1990年代に40~50代だった男女約6000人に性格テストを行い、毎日の運動量を記録。約20年後に再び同じ性格テストを実施しました。
その結果、普段の運動量の少ない人は、ビッグファイブの
- 誠実性
- 外向性
- 協調性
- 開放性
の得点が低かったことが分かりました。
この研究では、運動の負荷は関係なく、あくまでも運動量の低下が性格の悪化に関係しているとしています。なので、ガッツリ運動しなくてもOKです。
特に「マインドフルムーブメント」や「マインドフルウォーキング」などに取り組めば、相乗効果でより性格改善に役に立つと思われます。
自分の性格を受け入れる
逆説的に感じるかもしれませんが、「今の自分の性格をダメだ!」思うことは、マインドフルネス的ではありません。マインドフルネスは、
- いい悪いという評価判断を手放して、今この瞬間の
体験をありのままに観察することです。
つまり、今の自分性格はダメだ!と思うこと自体、評価判断につながり、結果としてマインドフルネスの効果が薄れてしまうんです。
マインドフルネスを実践する際中は、性格を変えたい!など目的意識は手放して、今ここの体験をあるがままに観察することに集中しましょう。結果論として、徐々に悪い性格が変わっていく可能性があると考えると考えましょう!
まとめ
マインドフルネスの実践は、自主性、協調性、誠実性などの性格を向上させ、不安感の軽減や自己受容につながることがわかっています。
特に運動との組み合わせが、性格改善には有効そう。ぜひ性格を変えたい!という意識はいったんわきにおいて、瞑想を淡々と続けてみてくださね。