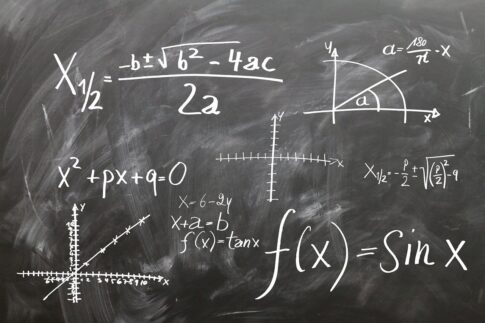まず初めにマインドフルネス自体には向き不向きはありません。マインドフルネスは心の科学であり、正しく実践するなら誰が行っても必ず心が成長していきます。
一方でマインドフルネスの捉え方ややり方を間違えてしまうことで、結果が出てないことがあります。
また実践するのが要注意な人もいるため、今回はこれらの部分について解説していきたいと思います。

Contents
マインドフルネスに向いている人の特徴4つ
1.自分へ思いやりがある人
僕自身、瞑想は始めた当初は、雑念が出てくるたびに
「やってしまったな」
「ダメだ…」
という気持ちが湧いていました。当然、瞑想は深まらず…。静かに瞑想していると思いきや、実態はただ目をつぶって座って苦悩しているだけの人。
ここで重要なのが、セルフコンパッションです。
ご存じの方も多と思いますが、セルフコンパッションは「自分へ思いやり」のことです。雑念が浮かんでも、「ああ雑念が生まれているな」と受け止めて注意を戻す。
この時に批判せず、ただの自然現象として理解し受けれ入れていきます。
自分への思いやりがある人は、今この瞬間を判断することなく瞑想に集中しやすい傾向にあるのです。

2.本気度が高い人
なんとくなく「瞑想って効果があるらしいから」「多くの人がやってるから」って気持ちで、瞑想に取り組むと全速力で肩すかしを食らう可能性が高いです。
- なんとしても、気づきを保つぞ
- 感情や思考に振り回されないぞ
- 今ここに集中するぞ
という「決意」が実践には必要になります。この決意がないと、集中力が落ちて中途半端な実践になりやすい傾向があります。
3. マインドワンダリング傾向が高い
マインドワンダリングとは、ざっくりいうと、心がさまよってしまうこと。つまり、マインドフルネスの逆の概念と捉えて良いでしょう。
「では、マインドワンダリングが高い人は、マインドフルネスに向いてないんじゃないの?」 と思われるかもしれません。 確かにマインドフルネスを深める上では、マインドワンダリングが少ない事は重要。しかし、雑念が多かったり、思考がさまよったりする方が効果を感じやすいんですよね。 きれいな部屋を掃除するよりも、散らかって汚れた部屋を掃除する方が、少し掃除しただけできれいになった感じが得られた経験はありませんか? 同じように雑念が多い方が瞑想がはかどりやすいのです。 これはマインドワンダリングとも関連がある話ですが、感受性が高い人もマインドフルネスの恩恵を受けやすくなります。 森(2024)では、心理臨床家の訓練としてのマインドフルネストレーニングの効果について調べました。その研究の1つにマインドフルネスと個人適性を調べたものがあります。 結果は以下のようになりました。 (※わかりやすいように表現を変えています) 美的感受性が高い人や動揺しやすい人(神経症傾向が高い)は、マインドワンダリング状態になりやすく、結果としてマインドフルネスの効果も得られやすいと考えられます。 マインドフルネスの効果が出にくい、向いていない人の特徴は、先ほど向いている人の特徴を逆にしたものが当てはまります。(※マインドワンダリングが高い意外) それらの他にも、向いてない人の特徴がありますので以下に紹介していきます。 これは多くの専門家が指摘する問題です。 私が見てきた中で最も早く挫折するのは、完璧主義的にアプローチする人たち。 「毎日必ず30分」 「雑念が浮かんだら失敗」 といった厳格なルールを自分に課します。 禅の世界には「努力無努力」という言葉があります。努力しているという意識さえ手放すことの大切さを表しています。マインドフルネスは「頑張るもの」ではなく「ただ気づくもの」なんです。 「私がスッキリすればそれでいい」という姿勢の人は、表面的なレベルで止まりがちです。 マインドフルネスの本質は、自分との関係性を変えることで、結果的に他者との関係も変わっていくこと。最初から「自分さえよければ」という動機だと、深いレベルでの変化は起こりにくいようです。 仏教実践では、戒(道徳)⇒定(集中力)⇒慧(智慧)という順で修行が進んでいくと言います。つまり、まずは道徳的にしっかりした人でないと、集中力発揮するのが難しくなるということ。 モテたい!金が欲しい!という気持ち否定する必要はないですが、あまりにも強い場合は、まず慈悲の瞑想をしたり、他人に貢献したりしてここに余裕を持たせることも大切です。 ブッダは「法を筏に例える」教えを説きました。川を渡るための筏であって、渡った後も背負い続けるものではない、と。 知識も同じです。いくら仏典を読んでも、心理学を学んでも、実際に座って瞑想しなければ何も始まりません。 私も最初は本ばかり読んでいました。テーラワーダ仏教の教え、認知科学の最新研究、禅の古典…。でも、実際に瞑想してみると、本の知識なんて役に立たない。体験こそがすべてだと痛感しました。 ブッダも「来て、見て、確かめよ」と言っています。理論ではなく体験なのです。 将来のことや目的にしがみつくと、そこに、 などが生まれてしまい、今この瞬間に集中できない可能性があります。 なぜなら、目的を持つこと自体が今の状態を 「不満」 「不幸」 などと捉えているからです。そして目的を達成してもまた新しい目的が生まれます。 もちろん、目的がある事は自然なことですが瞑想中は、その目的は一旦わきに置いて、今の瞬間に意識を向けつづけることが大切。 PTSDを抱えている人などは、マインドフルネス瞑想を行うことで、過去の「嫌な記憶」や「強いトラウマ体験」を思い出してしまう場合があります。 マインドフルネスでは自分の内面に注意を向けるため、思わぬときに辛い記憶がよみがえってしまうことがあるのです。 トラウマ体験のフラッシュバックが起こることで「強い不安を感じる」「パニックに陥って過呼吸になってしまう」といった危険性も示唆されています。 一人で行っているときにこのような状態になると、とても危険です。 一方で研究では、瞑想はPTSD症状や抑うつの軽減に長期暴露療法と同等に有用であり、PTSD健康教育よりも有用であることが明らかになりました、という報告があります。つまり、正しく行えばマインドフルネスはPTSDの症状を改善する効果があることがわかっています。 PTSDの人はマインドフルネス実践は要注意ですが、やり方次第ではつらい過去の克服にもつながります。グラウンディングなどで安心感を保ちながら実践していくのがよさそうですね。 マインドフルネスには向き不向きがあり、特に、ADHDの人やトラウマなどを抱える人にとっては、実践には注意が必要。一方で、それ以外の向き不向きは、実践の仕方によって変えられるので、毎日の生活の中で、少しずつ身に付けてみてください! 僕も雑念が浮かんだときに、自分を責めがちなので、その点が課題ですねー。 どちらかというと向いてない側かもなので精進します(笑)4.感受性の高い人
マインドフルネスに向いていない人の特徴4つ
1.頑張りすぎる人
2. 自己中心的な人
3.知識的な人
4. 瞑想に過度に期待する
PTSDやトラウマを抱える人は要注意
フラッシュバックが起こる可能性
パニックになることも
マインドフルネスがPTSDに効果があることも
まとめ